1983/9 No.2 |
1. インターノイズ83に参加して | 2. 国際音響会議(ICA) | 3. 音響的手法による航空機機種別の試み | 5. 植込型人工中耳 | |||||
| 6. フランス新幹線・TGV | 7. CEPの騒音研究施設 | 8. 土地利用の適合性を決定する環境条件 | |||||||
理事長 五 十 嵐 寿 一
第11回国際音響学会議は、英国、エヂンバラにおけるインターノイズに引きつづいて、昭和58年7月19日から7月27日までフランス・パリで行われた。
ICAは音振動を主題としたインターノイズに対し、音響学全般を対象として3年毎に行われる。
| 第1回 : | デルフト(オランダ) | 1953年 |
| 第2回 : | ボストン(米国) | 1956年 |
| 第3回 : | スツットガルト(西ドイツ) | 1959年 |
| 第4回 : | コペンハーゲン(デンマーク) | 1962年 |
| 第5回 : | リェージュ(ベルギー) | 1965年 |
| 第6回 : | 東 京(日本) | 1968年 |
| 第7回 : | ブタペスト(ハンガリー) | 1971年 |
| 第8回 : | ロンドン(英国) | 1974年 |
| 第9回 : | マドリッド(スペイン) | 1977年 |
| 第10回 : | シドニー(オーストラリア) | 1980年 |
| 第11回 : | パリ(フランス) | 1983年 |
次回第12回はトロント(カナダ)で行われる予定である。今回は1250名の参加者と約700の論文発表が行われた。本会議の前にサテライトシンポジウムとして、音声(ツールーズ)、固体の振動から発生する音(リヨン)を主題として行われた。
開会式はソルボンヌ大学の大講堂において、今回の会議の議長Prof. Lehmanの開会宣言に始まり、政府代表環境大臣Mme. Rouchardeの歓迎の辞およびICA会長Prof. Beyerの挨拶があった。
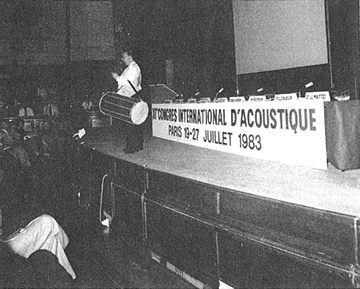 |
本会議はパリ西南部のホテル・ソフィテルにおいて、8〜12会場を使って併行して進められた。会議は発表論文のほかに、各分野毎に特別講演が行われた。
最初に、ICAの直前に各地で行われた会議のまとめとして、次の報告があった。
| 1)騒音の影響に関する会議(イタリア、トリノ) | |
| Prof. H. W. Jansen. | |
| 2)サテライトシンポジウム | |
| 音声(トウールーズ) | |
| Dr V. Zue. | |
| 固体音(リヨン) | |
| Prof. C. Lesueur. | |
| 3)インターノイズ(エジンバラ) | |
| Prof. J. B. Large. | |
| 4)超音波(ハリファックス) | |
| Prof. H. W. Jones. | |
このほか、最近注目される話題について毎日2題ずつ、つぎの講演があった。
| 1) How we hear. | |
| Prof. N. Y .S. Kiang. | |
| 2) 絶対零度近くにおける液体ヘリウムの中の量子音響学 | |
| Prof. I. Rudnick(USA) | |
| 3) 海中における低周波暗騒音 | |
| Prof. B. F. Krianov. | |
| 4) 電気音響変換器. 現在と将来 | |
| Prof. G. Sessler. | |
| 5) 半導体結晶の光音響分析法 | |
| Prof. Mikoshiba. | |
| 6) 音響学における音源の問題 | |
| Prof. E. J. Richards. | |
| 7) 新しい音楽における音の数値合成の進歩 | |
| Prof. J. C. Risset. | |
| 8) 非線形流体音響学 | |
| Prof. Timochenko. | |
| 9) 音響学における数理的手法 | |
| Dr. T. Seznec. | |
| 10)音響光学の50年 | |
| Prof. R. Mertens. | |
また、最近注目されている課題についてStructural Iectures及びRound table meetingsとして、事前にOrganizerを指名して関連分野の研究発表が計画され、これらについて活発な討論が行われた。騒音振動の分野で注目されるものとして、“Active sound absorber”“Optic fibre acoustic detector”“Intensimetri and characterization of sound sourcec”などがある。特にOptical fibreは今後の新しい音響の“transducer”として期待される。また音響インテンシティ法は最近応用分野のひろがった問題であり、“Actives sound absorption”は古くからいろいろ試みられた問題であるが、最近の計測技術の進歩をうけて特に低周波の騒音対策として注目されている課題である。
研究発表は6日間、8〜12会場に分かれて行われたが、超音波から可聴音にわたる音の伝般の問題、衝撃音を中心とする音の評価の問題、最近の計測技術を用いた信号処理などの発表が多くみられたこと、また音楽音響の分野の発表が多かったことなどが特徴である。
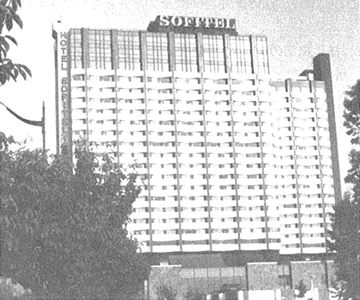 |