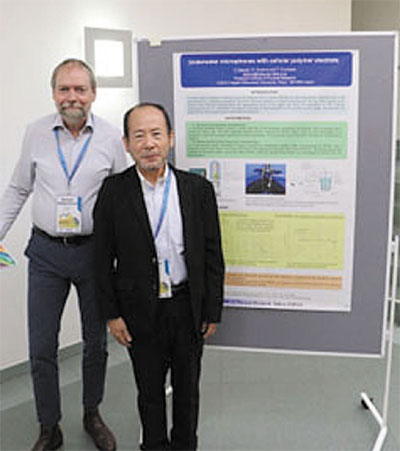|
2024/ 1
No.163 |
1. 巻頭言 | 2. 101 歳の物理学者の回想 | 3. 19th International Symposium on Electret(lSE19)会議報告 | 4. 自身の聞こえに関する「気付き」を促進するための「聞こえチェッカー」の開発 | |||
|
|
5. 携帯ワイヤーレコーダ | ||||||
<会議報告>
![]() 19th International Symposium on Electret(lSE19)会議報告
19th International Symposium on Electret(lSE19)会議報告
理 事 安 野 功 修
第19回IEEE International Symposium on Electrets(ISE)が去る9月18 日より22 日の5日間にわたって、オーストリア・リンツ市で開かれた。会議はBildungshaus Sankt Magdalena でJohannes Kepler University Linz, Soft Matter Physics Groupの主催で行われ、Invite 18件、Oral 36 件、Poster 20 件の計74 件、Electroactive polymer for soft transducers をテーマにWorkshop 5件が実施された。参加登録者は90 名17 か国(うち日本人15 名)。
ISE は、世界中から科学者、エンジニア、若手研究者が集まるこの分野の主要イベントである。パンデミックによる4年間の休止期間を経て、久しぶりにエレクトレット コミュニティが再開された。今回開催されたリンツ市はドナウ川沿いの商工業都市で、ウィーンから西に150 km に位置しオーストリア第3の都市である。ケルト時代にまで遡る長く波乱に富んだ歴史があり、ナチス・ドイツによるオーストリア併合がされた舞台としても知られている。
会議はEducational Center のセミナールームでオーラル発表、その入り口フロアでポスター発表が実施された。開催前日の夕方より受付が始まり、ウェルカムパーティが屋外テラスで催され、旧交を温めアットホームな雰囲気で始まった。初日はBernhard Gross Memorial Award 授賞者の講演から始まり、2005 年以来ISE 分野における継続的で質の高い研究活動で国際的な評判を確立している研究者に授与された(2019年には当所の古川猛夫特別研究員が受賞)。今回は、前回中国・上海の ISE18 で選出されたProf. Heinz von Seggern の講演があり、その講演の中で、1966 年にSessler とWest が永久静電荷を蓄えたFEP ポリマーエレクトレット(テフロン)のマイクロホンへの応用を発表し、1970 年代に商用化されて以来50 年間の歳月で総数295 billion のエレクトレットマイクロホン、総額229 billion USドルのPP(Polypropylene)フィルタが生産されたことも紹介された。その後Session 1 ~ 12 が4日間にわたって行われ、最後にワークショップで終了となった。
当所からは、古川特別研究員がInvited Paper として “Towards quantitative understanding of phase transition and polarization switching in VDF-based ferroelectric polymers.”を講演し、フッ化ビニリデンとテトラフルオロエチレンのコポリマーの強誘電性について、強誘電体から溶融相への転移、反強誘電相と常誘電相は分子間および分子内および結晶双極子の秩序が連続的に失われることによって発生するメカニズムを概説した。Poster sessionにおいては安野が“Underwater microphone with cellular polymer electrets”と題して発表し、海棲哺乳類を保護する観点で水中騒音評価の必要性が増してきていることから、可聴域での人工騒音測定を目的としたCellular-PPの水中マイクロホンへの応用について報告した。また、東京理科大の菅野さんは“Study on piezoelectric properties of ferroelectric Nylon 11 film”を発表した。これは児玉主任研究員との共著で、強誘電性ポリマーナイロン 11 の誘電率、弾性率、電気機械結合係数、および圧電定数の温度依存性が広帯域誘電分光法を使用して系統的に評価したもので、電気機械結合係数は180 ℃の温度範囲まで緩やかに変化し、ナイロン 11 が優れた熱安定性を示すことを報告したものである。この研究は若手科学者の最優秀口頭発表およびポスター発表に贈られるディリップ・ダス=グプタ賞を受賞した。
シンポジウムの中間日には Prof. Siegfried Bauer(Prof. Siegfried Bauer は 2007 年に当所ピエゾサロンでCellular-PPを紹介された先生)を偲んで特別Session が設けられ、Bernd Ploss, Reimund Gerhard, Michael Wubbenhorst, Reinhard Schwodiauer4名の追悼講演が行われた。午後からはExcursion としてVOESTALPINE STEEL WORLDの見学が企画された。1949 年に軟鋼製造における最も重要な革新がリンツで行われ、溶融銑鉄が酸素ランスの挿入によって脱炭される軟鋼を製造するプロセスは、現在世界中で使用されていると説明があった。
今回の会議において全体的に、従来の分野でのReviewと新材料の報告に対してEH(Energy Harvester)関連の材料、トランスデューサの提案等が増えてきている印象である。特にエレクトレット化するための方法として、従来の方法とは異なる、材料分子のイオンバランスを崩して負電荷を永久帯電させる方法、或いは荷電処理が一切不要の自己組織化エレクトレット(Self-Assembled Electret : SAE)を振動EHに応用する等の新たな方向性を示唆する発表が、実用化に近い研究として注目された。