|
1997/10
No.58 |
1. 交通騒音対策の21世紀にむけての課題 | 2. Active 97, Inter-Noise 97 in Budapest参加報告 Active 97編 | 3. Active 97, Inter-Noise 97 in Budapest参加報告 Inter-Noise97編 | 4. 医薬用微粒子計 |
−Inter-Noise 97編−
騒音振動第三研究室 廣 江 正 明
Active97に引き続きInter-Noise 97が8月25日から27日の3日間ハンガリーの首都ブダペストで開催された。ブダペストは街の中心を南北に流れるドナウ川を境に王宮や公園が広がる西のブダ地区と市場や繁華街がある東のペスト地区に分かれている。Inter‐Noise 97の会場には、ドナウ川に面し中心街に近いブダ地区のブダペスト工科大学が当てられた。
旧東欧のハンガリーがInter‐Noise 97開催地に選ばれたためか、日本からの参加者は例年に比べて少なく、名簿上では全参加者647人中で僅かに59人だった。我々小林理研からは山本研究企画室室長、田矢騒音振動第一研究室主任と私の3人が参加した。国際会議での発表は3年前に横浜で開かれたInter‐Noise 94に続いて2度目だが、海外での発表はこれが初めてである。前回は発表するのが精一杯で質疑応答では質問が聞き取れなくて何も答えられず、非常に恥ずかしい思いをした。今回はそんな事のないように半年前から英会話学校に通い、会話や聞き取りが出来るように努力した(つもりである)。しかし半年程度で十分な英会話能力が備わるはずもなく、非常に不安な出発となった。
当所からの発表論文は、
田矢"Laboratory experiment on the impression of river
flow sound"
廣江"An investigation on sound emission from a high-speed
moving source"
の2件で、田矢は"Environmental noise‐General"のセッションで、私は"Vehicle
noise‐Railbound vehicles"のセッションでそれぞれ発表した。我々の参加した一般講演は発表が15分、質疑応答が3分、その他(発表者の交代時間)2分の合計20分で行われた。ただ二人の発表日時が共に学会2日目の17時40分と全く同じで、幸か不幸か互いの発表を聞くことはなかった(二人の発表を心配して、互いの会場を往復した山本氏が一番大変だった…)。
今回の滞在期間はアーへン工科大学の施設見学とActive 97への参加を合わせると8月18日から29日の11日間、その内ハンガリーには8日間と非常に長期であった。そのお陰でInter‐Noise 97が始まる25日(月)頃には日本との時差の影響も十分に解消され、体調は万全だった。ただ30度近い暑さの日がほとんどで、真面目な(?)我々も暑さに耐えかねて、特別な時以外は上着無しで会議に参加していた。
ところで今回Active 97やInter‐Noiseに参加して驚いたことは、発表原稿を読む人はごく一部で、大部分の人が時折原稿を見る程度で、原稿をほとんど暗記していたことである(中には発表原稿を持たない人もいた)。当初、本番では発表原稿を見ながら正確な発音とイントネーションで落ち着いて発表すれば良いと考えていた。しかしこれらの発表を聴いてみると、ある程度原稿を暗記した発表の方が落ち着いていてスムーズであり、またその方が単に原稿を読むよりも何倍も良い発表であった。そこで(多少無謀な気もしたが)我々も発表当日までに原稿を覚えることを目標にがんばることにした。Inter‐Noise 97の初日、大学の講堂でオープニング・セレモニーが盛大に行われた。General Chairmanを務めるAndras Illenyi氏やI-INCE会長W. W. Lang氏等の挨拶の後に開かれたWelcome Concertで、ハンガリーの歌と器楽曲(チェンバロに似た楽器による二重奏曲)を堪能することができた。地元の音楽を聴くのは初めてであり、器楽曲の緻密なアンサンブルと椅麗な歌声にとても感動した。
オープニング・セレモニーに続いてInter‐Noise 96でGeneral Chairmanを務めたUK National Physical Laboratory(NPL)のB.F. Berry氏が特別講演を行った。講演の内容は、過去70年間にNPLが貢献した国内および国際基準に関する諸研究の紹介で、当時の音響機器や計算機の様子、研究に伴う様々な苦労や工夫についての講演でした。その巧みな話術で会場は非常に和やかな雰囲気に包まれ、1時間の講演時間はあっという間に過ぎ去り、午前のプログラムは無事に終了した。
午後からは招待講演を含む一般講演が9つの会場に別れて始まった。この日の午後、第9会場で夕方まで''Noise control elements−Barriers"のセッションを聞いた。このセッションでの発表の大きな特徴は、そのほとんどが鉄道騒音に関連する防音壁の研究で、かつ転動音を対象にした研究が多かったことである。主な発表内容は、列車近傍に設置した低防音壁の減音効果、TGVを対象にした防音壁形状の研究、2次元境界要素法を用いた防音壁の減音効果の計算である。転勤音を対象にした研究が多いのは、欧州では日本と異なりピークレベルLAmaxではなく等価騒音レベルLAeqで鉄道騒音の評価を行うためと考えられる。
さてこの日は、夕方から大学構内の食堂で開かれたWelcom Partyに出席した後、遅くならないうちにホテルに戻り、発表練習を2回行った。
2日目。とうとう発表の日がやってきた。昨夜の練習だけでは心もとなく、午前中はホテルの自室で実際にOHPシートを指し示しながら何度も発表練習をした。私の参加する"Vehicle noise‐Railbound vehicles"のセッションは、第3会場で午後1時50分から始まる予定になっていた。結局、一度も満足な発表練習ができないうちに会場に行く時間がきた。最悪である。
私の発表は12人中の11番目で、座長はDr.Kurzeであった。前日の防音壁に関する研究と同様に、車輪とレールに関する研究、すなわち転動音を対象にした研究が多かった。初めは他の講演を熱心に聴くつもりでいたが、頭の中は自分の発表で一杯で熱心に聴く振りをするのが精一杯であった。
やがて午後の発表も一人二人と終わり、とうとう自分の順番が回ってきた。平静を装っていたが、実は今にも心臓が口から飛び出しそうで、"l will be right back!(すぐに戻ります)"と嘘をついてこの会場から出て行きたい心境だった。すると座長のKurze氏が「君は2日目の発表でよかったよ。明日の今頃はもっと悪い状況で発表することになるから。」と声をかけてくれた。よく見るとセッションが始まった頃に比べてかなり聴衆の数が減っていた。「確かに!」などと会話する内に気持ちが幾分落ち着いてきた。
開始のチャイムが鳴ってからの15分はあっという間に過ぎた。完全に発表原稿を暗記していなかったため、途中で何度か原稿を読む場面もあったが、何とか無事に最後まで辿り着いた。座長Kurze氏から一つ二つ質問されたが、片言の英語で何とか答えることができた。発表の後で、時田先生や山本氏から「良かったよ。」、「上出来や。」と言われてほっとした(その後のビールの旨かったこと)。
最終日は、Active 97でGeneral Chairmanを務めたDr. Augusztinoviczの「数値計算手法を用いた騒音制御の予測」に関する特別講演を聴いた後、Dr.Vorlanderの招待講演を聴きに行った。アーヘン工科大学を見学した折、Inter-Noise 97での再会を約束していたので、どうしても聴きたかった。講演内容は離しく良く判らなかったが原稿を持たずに発表するスタイルは、自分たちが目標にしていたものと同じであった。発表は初めの導入部分に若千時間をかけ過ぎたためか、時間が足らなくなり、最後は何枚かのOHPを残して十分に結果を議論しないうちに結論を述べていたが、その時々に対応した発表が出来るのはさすがだと感心した。
今回、Active 97とInter-Nise97に参加して印象に残ったのは、自分の発表をより多くの人に理解してもらうために、大部分の発表者が原稿を覚えた上で発表を行っていたことである。中には上手に発表できなかった人もいたが、それでも自分の言葉で何かを伝えようと必死で発表している気持ちは十分に伝わってきた。今度参加する時には、必ず発表原稿なしで発表できるようにしたい。次回のInter-Noise 98は1998年11月16日から18日の3日間、ニュージーランドのクリストチャーチで開催される予定である。
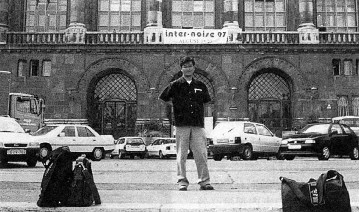 |
|
ブダペスト工科大学(Inter-Noise 97の会場)前で
|