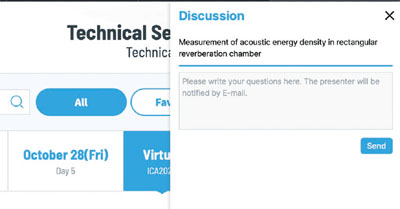|
2023/ 1
No.159 |
1. 巻頭言 | 2. ICA2022 | 3. BA-S型振動子の計測への応用 | |||
|
|
||||||
<会議報告>
![]() ICA 2022
ICA 2022
建築音響研究室 杉 江 聡、豊 田 恵 美
ICA 2022 が10月23日(日)~ 10月28日(金)の6日間、韓国の慶州(Gyeongju)で開催された。ただし、新型コロナウィルス感染症蔓延の防止のために、オンラインでの配信を含めた、いわゆるハイブリッド形式の会議となった。オンデマンド配信期間は、10月24日(月)~11 月13 日(日)であった。慶州は、ソウルから高速鉄道で2時間強の朝鮮半島の南東部にある都市である。1~9 世紀には新羅王朝の首都であったために、3つのユネスコ世界遺産があるそうで、非常に風光明媚で、歴史を感じる街だろうと想像される。会議は、普門湖のほとりにあるHwabaek International Convention Center (HICO)で行われた(図1)。
現地発表者は事前に発表を録画した動画ファイル(最大12 分間)を事務局に送付するシステムである。一方、バーチャルでの発表視聴方法は、これらの動画を視聴するのに加え、図2に示すように現地でのタブレットPC等で録画した動画を視聴することができる。国内で行われる一部の会議のようなリアルタイムに質疑を含めた発表視聴方法ではなかったが、国際会議なので、世界中からの参加者を考えると、時差を考慮しないといけないので仕方がないことである。しかし、この動画のアップロードが発表の翌日であり、会議期間中に発表を視聴でき、その上、その動画には質疑も含まれており、実際に参加したのと近い感覚を覚えた。
バーチャル形式は、参加意識が低下するとよく言われる。私も、オンデマンド配信終了日が当初の11月5日から11月13日に延長されていたのをこの原稿執筆まで知らなかった。その理由として、バーチャル参加ではオフィスにいたたままで参加でき、時間を有効に使える一方、日常の時間の流れの中で参加することになり、現地に赴くという非日常を体験することができないことが挙げられるのではないだろうか。国際学会にかかわらず、様々な研究者や技術者と、会場だけなく色々な場所で語り合うというのが研究発表会の本質の一つだと思う。次は、クリックひとつで現実に引き戻される会議ではなく、生な音声が聞ける国際学会に参加したいと思う。
(建築音響研究室長 杉江 聡)
久しぶりの国際学会参加であったが、開催地に行くことは叶わず、バーチャル参加者として会議に臨んだ。特設サイト上には、バーチャル参加者が事前に投稿したビデオが閲覧できるようになっており、また現地の発表者のビデオは、発表の次の日にはアップロードされていた。現地のビデオは、画面いっぱいにスライドのみが録画されていて、発表者や座長の姿等、会場の様子は映されていなかった。また質疑応答の部分は録画に含まれていないビデオもあり、現地の雰囲気が伝わらないのは非常に残念であった。せめてWelcome ReceptionやPlenary Lectureだけでもオンタイムで視聴できれば、少しは国際学会気分が味わえたのではないかと思う。
業務の合間に時間を見つけては、建築音響と室内音響のセッションを中心に可能な限りビデオを視聴した。遮音吸音に関する発表は比較的少なかったように思うが、木造建築、特にCLT(Cross Laminated Timber:直交集成板)に関する発表は多くみられた。また韓国開催ということもあってか、床衝撃音関係の発表は多くみられ、韓国でのゴムボールを用いた測定に関する検討や、各国の測定規格に関する研究動向等は興味深かった。
また、現地参加では自分のメイン分野のセッションの会場に出席していることが多いが、普段は聞きに行かないセッションの発表も気軽に視聴できるのは、バーチャル参加の良いところだったように思う。個人的には、教会等の文化遺産の音響に関するセッションは面白かった。
私は、子供たちが日常生活を送る音環境を改善する取り組みとして、保育園で使用することを目的とした、簡単に手作りできる吸音体に関する検討を発表した。今回のビデオ投稿という形式は、発表時間内に収めるプレッシャーや質疑応答の異常な緊張状態を回避できるという意味ではありがたく感じた。しかし、せっかく時間をかけて作ったビデオも、どれくらいの参加者に視聴してもらえたかも分からず、図3のように質疑応答は特設サイト上に設置されたチャットで対応するシステムになっていたのだが、結局1件もコメントをもらうことができず静かに会期が終了してしまった。メールで直接質問が来ないかと少し期待していたのだが、それも無く、あまりの手応えのなさに虚しさだけが残った。どんなに緊張で胃が痛くなっても、直接議論しなければ意味がないのだと、改めて実感した。
(建築音響研究室 豊田恵美)